
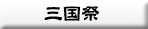 |
 |
|
 |
|
県
指定
無形民族文化財
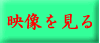
|
北陸三大祭のひとつとして称せられ、毎年5月19日〜21日にかけておこなわれ、10数万の参拝者で街中がにぎわう。神輿2基神宝棒持の行列、武者行列に名物の武者人形山車6基が港町の情緒をかきたてる。狭い町並みの両脇にぎっしり立並ぶ700軒の露店商、人々の波で街中が祭一色になる。20日の正午に三國神社前に奉納された山車6基、午後1時に山車神輿の行列が神社前から街中に繰り出す。
これにたづさわる奉仕者700人、三国っ子は燃えに燃える。
立並ぶ露店商の屋根をハネ上げ、ハネ上げ笛と三味線、太鼓の囃子で山車が進む。きしむ車輪の音。面かじ取りかじの聲の中、250年の歴史を刻んできた山車・神輿と武者行列の巡行である。この日は、全町内が休日で夜9時ごろまで巡行は続く。 |
|
|
|
|
|
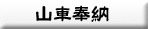 |
|
・三国祭の山車は18基あるが、そのうち毎年6基が奉納される。神社に近い古い区は当番が早く3年に1度まわってくるが6年8年に1度という区もある。
・三国祭の中日祭である5月20日の午前10時から12時までに当番区の山車が三國神社前に1番から6番まで勢揃いして奉納する。
午後1時に、神輿をはさんで前後に並び、神社前を出発し、旧三国町内を区民全員が自分の区の山を曳いて巡行する。
|
|
|
|
|
|

当番区が三国神社に奉納するために制作しました山車(やま)6基をご覧ください。
|
壱番山車

|
弐番山車

|
|
森町区 木村重成(きむらしげなり)
木村重成は、大坂冬の陣、夏の陣にて豊臣方の重臣として活躍した武将で、後藤又兵衛、真田幸村、長曾我部盛親らとともに豊臣4天王、また豊臣7人衆と呼ばれました。
|
玉井区 真田幸村(さなだゆきむら)
真田幸村は戦国時代に活躍した武将で、赤の甲胃に身を包み、両手で槍を構えた勇壮な立ち姿となっております。豊臣方として大坂夏の陣での活躍と華々しい最期が、後に「日本−の兵」(ひのもといちのつわもの)と評されました。
|
|
| 参番山車

|
四番山車

|
下台区 明智光秀(あけちみつひで)
明智光秀は戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。越前国の朝倉義景氏をたより、坂井郡(現在の丸岡町長崎)の称念寺門前に居をかまえていたと言われています。その後、足利義明や織田信長に仕えその才覚で大名にまで出世しました。
天正15年(1582年)「本能寺の変」で主君信長を何故討ったのかは、日本史の大きな謎となっています。
|
三国祭保存振興会 羅城門
謡曲「羅生門(羅城門)」は、羅生門に巣くう鬼と戦った渡辺綱の武勇伝を謡曲化したもの。平安時代の中期、源頼光の頼光四天王の一人渡辺綱は、王地の総門に鬼が住む謂れはないと言い、それを確かめるべく単身羅城門へ向かった際、鬼の奇襲を受け、決闘の末に鬼の腕を切り落とそうとする場面を表しました。
|
|
|
五番山車

|
六番山車

|
|
真砂(上真砂・下真砂)区 渡辺綱(わたなべのつな)
平安時代中期の武将。通称は渡辺源次。頼光四天王の筆頭として知られる。渡辺氏の祖。
源頼光が家来の渡辺綱・坂田金時・碓井貞光・卜部季武を引き連れて大江山に出向き酒呑童子一味を見事討ち果たす大江山の酒呑童子退治は御伽草子などで後世に伝わる。
|
上ハ町(平野・久宝寺区) 鏡獅子(かがみじし)
鏡獅子は春興鏡獅子(しゅんきょうかがみじし)といわれる舞踊劇です。 舞台は江戸城大奥、正月の鏡曳きの余興で小姓の弥生が舞っている途中で獅子のせいが乗り移り、胡蝶の精と舞い踊ります。前半の可愛い女の子の踊りから後半は勇壮な獅子へ、華やかで楽しい演目です。
|
|
|
| ▲このページのトップへ |
|
|
|
|
|
|
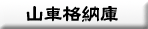 |
|

中元区山車格納庫 |

松ケ下区山車蔵 |
・毎年5月20日に町中を練り歩く三国祭の山車の常設格納庫は現在16棟あります。今年の三国祭にはこの山車蔵からも武者人形山車が町内に繰り出します。
・「 松ケ下区山車蔵」は、三国祭終了後も観光客の皆様に山車人形を常時展示して見学出来るように前面の観音扉をガラス入りにしています。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
三国祭の歴史は古く、遠く江戸時代中期までさかのぼる。当時の祭礼の様子は明らかではないが、元禄10年(1697)の『大門町記録』に「傘鉾、1本浄願寺の縁の下にあり」と記されてあり、これが三国祭に関する最古の記録である。
宝暦3年(1753)の『町々山覚』によれば、この年、山車の行列の順番を割り振って1番から10番までの山車を出している。この記録は武者人形を飾る以前の山車の状況を示す資料であるが、ここに、6番山車にあたる上町で神功皇后を作っていることが記されているが、これが現在の武者人形の起源である。
三国祭の祭礼日は、旧暦の4月「申の日」を祭礼日として継承されてきた。
新暦(太陽暦)を採用後の明治6年に祭礼日は『毎年5月20日』と定められ今日に至っている。三国祭の行事は神仏分離以前の江戸時代以来の伝統習慣を今日に伝えるもので他にあまり例を見ない興味深い行事を継承している。 |

鳥居横の明治40年頃の
飾山車 |
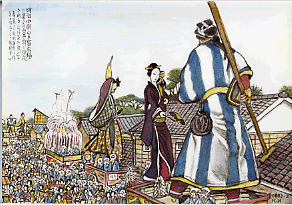
明治中期の山王宮広場に集まった山車奉納図
|
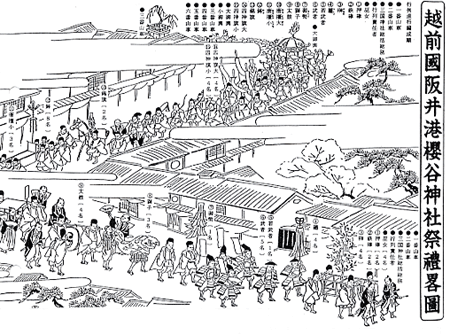
寺島孫四良作:木製版画:
明治4〜5年頃の風景:行列役員の頭にちょん髷がある |
|
|
|
|
|
|
|
|



